Autumnal
皇子様とアラビアンナイト
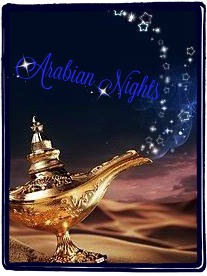
――――
――
遠くでポチャン、ポチャン…と水が落ちる音がする。
その音は不快で……まるで耳鳴りのように俺の耳朶を刺激する。その音から耳を反らそうとしていたときだった。
「Open heartedly,Kou.(心を開いて、コウ)」
向かい合って座っているステイシーが俺の頬をそっと撫でてきた。
彼女の手がいつになく熱いのは、ここがバスタブだからだろうか。あの不快な音もステイシーが触れてくれると、自然に耳鳴りが収まってきた。
そう
俺とステイシーは今二人で風呂に入っている最中だった。
マンハッタンの彼女のアパートのバスルーム。決して広いとは言いがたいバスルーム。
そのバスタブで泡を浮かべたバブルバスの湯に二人で良く入った。
遠い記憶だ。
「It's open.(開いてるよ)」
泡のくっついた彼女の手がくすぐったくて身をよじると、逃げ出そうとする俺の頬をしっかりとホールドしてステイシーの蒼い澄み切った目が真剣に俺を捉える。
「No,open.(開いてないわ)Please look at me,Kou.(コウ、私を見て)」
Take yourself seriously.(私は全てを受け止めるから)
Sweetie pie.(私のかわいこちゃん)Please.(お願いよ)」
ステイシーが僅かに体を起こすと、俺の額にチュっとキスを落とす。
そのまま顔ごと抱き寄せられ、彼女の白く柔らかい豊かな胸へと導かれた。
「Please」
ステイシーの声が遠くでエコーしているのは、ここが風呂場だからだろうか。
『心を開いてください、ミスター来栖。今のように―――』
これは誰の声だろう。
ああ、そうだ。秋矢さんの声だ―――
P.104
目を開くと、そこは白い高い天井が広がっていた。
「ここ、どこだ……?」
ゆっくりと頭を動かすと、ズキリ!俺の頭に激痛が走った。まるで殴られたときのような衝撃に顔をしかめる。
「ってーー…」
涙目になって滲む視界の中、ゆっくりと辺りを見渡すとそこは俺に与えられた宮殿のお部屋だと分かった。
鉛が詰まったような重さの頭を何とか起こし、半身を起き上がらせると
自分が今ベッドの上で寝ていた、と言う状況がようやく飲み込めた。
え??何で??
確か昨夜は秋矢さんと日本食が食える居酒屋に行って―――
久しぶりに食べる刺身や天ぷらや煮物がやたらとうまかったのは覚えているが、それ以外のことは……
「ヤッベ……記憶ねー……全然覚えてない」
俺は痛む額を押さえて必死に記憶を掘り起こした。
確か中ジョッキの生ビールを三杯と、芋焼酎のロックを一杯、そして日本酒の熱燗を一合飲んだところまでは記憶にある……
けど、その後の記憶がプツリと途切れている。
「ちゃんぽんしたのがいけなかったのかなー…前はもっといけたんだけど……
てかここに運んでくれたの、きっと秋矢さんだろうなー…
あの人も同じだけ飲んだのに、化け物か」
はぁ…
ため息を吐くと昨日の酒がまだ抜けていないのか、僅かに口の中がアルコール臭い。
「俺、サイアク」
P.105
それから半日、俺はベッドから起き上がることができなかった。
何とか頭痛が引いてシャワーを浴びると、いくらか酒臭さが消えた気がする。
さっぱりしたところで部屋を出て、水を貰おうと広間に向かうと、その途中の廊下の隅でカウチに腰掛けた秋矢さんと出くわした。
秋矢さんは長い脚を組んで英字新聞を開いていたが、俺を見ると新聞を畳んだ。
ほとんど初対面で、しかも大先輩を前に酔っぱらって記憶なくすとか、失態にもほどがある。
何となく顔を合わせづらくて、俯いたまま
「お、おはよーございます…」と小声で挨拶すると
「おはようございます。と言ってももう昼ですが。
だいぶ酔っぱらっていらっしゃったようですが、もう大丈夫ですか?」
と秋矢さんはいつものポーカーフェイスで淡々と聞いてくる。
あ、やっぱこの様子だと運んでくれたの秋矢さんかー。
てかこの人、あんなに飲んだのにケロっとしてるし、やっぱ化け物。
「昨日は!もう、本当にすみませんでした!!」
俺はもう頭を下げて謝ることしかできない。
P.106
この歳になって泥酔とか、みっともなくて恥ずかしくて顔を上げられない。
「いいえ、お気になさらず」
秋矢さんがクスっと喉の奥で笑ったから
「あの……俺、変なこと言ってませんでしたか?」
目だけを上げて聞くと、
「‟くたばれ”と言われましたが」と秋矢さんはさらり。
「それはちゃんと覚えてます。あのときは大変失礼いたしました。でも俺が知りたいのはその後―――」
「ああ、『秋矢さんのバカ、アホ、死んじまえエロ河童』と言っていましたが」
ぇえ!!俺そんな酷いことを!!ヤバイ!!全然記憶にない!
「あの…!それは本心ではなく…!」
酔った勢いってもんで~と説明したかったが、
「冗談ですよ」
秋矢さんはまたもクスっと意地悪そうな笑みを浮かべ、
へ!冗談!?
「あなたは天使のようなお顔で、それはそれは気持ちよさそうにぐっすりとお眠りでした」
「また冗談ですか」
またこの人は!俺をからかって楽しんでやがる。
秋矢さんは笑いながら立ち上がると、俺に顔を近づけ、本能的に一歩後退した俺の腰を両手で掴むと、
「It was nonetheless true.(本当のことですよ)」
耳元でそっと囁いた。
P.107
秋矢さんはそれ以上何かをしてくるわけでもなく、すぐに俺から離れると
「さ、皇子がお待ちかねです。どうぞ、お行きになってください」
と、促される。
言われるがままに……と言うか一々秋矢さんに怒ってるのも疲れてきた。
俺は素直に頷いて、執務室に向かった。
「オータムナルさま、失礼します」
執務室に入るのは昨日の授業以来だ。そんなに時間が経ってないのに、やっぱりここに入るときは緊張する。
オータムナルさまは昨日と同じようなスーツ姿で、同じように執務机の上に頬杖をついて俺を待っていた。
「おはよう紅」
紅―――
ただ単に名前を呼ばれただけなのに、何故か俺の心臓がドキリと打つ。
「お、おはようございます」
慌てて挨拶をして
「お、お体の具合はいかがですか?」
とついでのようにさらりと聞いた。
「具合?ああ、絶好調だが。何故そのようなことを聞く」
「あ、えっと……昨日お医者様がいらしてたみたいなのでどこかお悪いのかな~とか……」
秋矢さんは勘ぐるな、と言っていたが聞かずには居られなかった。
だって心配だもん。
「私は至って健康だ。医者が来たのは単なる定期健診だ」
定期健診……って健康診断みたいなものかな。
王族ともなるとヘルスケアもしっかりしないといけないんだろうなー。
まぁ今日のオータムナルさまを見てると、どこか悪そうに見えないから本当のことだろう。
良かった―――
なんて考えてると、オータムナルさまはそっと立ち上がり、俺の元へゆっくりと歩いてきた。
高級そうな革靴の音がフローリングを打ち、その心地よい音を聞いているうちに
あっという間に俺の頭上に影が降ってきた。
「お前は、私の心配をしてくれたのか」
「え?ええ……でもどこも悪くないことを知ってほっとしました」
俺がにこにこ言うと、オータムナルさまも同じ笑顔を返してくれる
と、思ったのに―――彼は形の良い眉を下げて切なそうにサファイヤブルーの瞳を揺らした。
「紅」
名前を呼ばれて、
「はい?」顔を上げると
「抱きしめて―――良いか」
突然聞かれた。
P.108
え――――……
「えっと……」
何て答えていいか分からずおろおろしていると
ふわり
甘さと重さを絶妙に混ぜ合わせた不思議な―――それでいて爽やかな紅茶の香りが俺を包んだ。
オータムナルさまは俺の体を抱きしめると、俺の肩に頭を置く。
「お……オータムナルさま……」
「お前の体温―――気持ちよいな」
耳元でくすぐるような低温が囁く。触れていないのに、その場所から熱が全身に行きわたり甘い痺れが走った。
「えっと……それはありがとうございます」
オータムナルさまはその答えに何も返さず、ぎゅっと俺を抱きしめたまま瞳を伏せた。
長い睫が俺の首をくすぐるように掠める。
俺は―――おずおずと彼の広い背中に手を回し
「オータムナルさま……」
彼のうなじにかかる上質な金糸のようなプラチナブロンドの少し長めの襟足にそっと触れた。
その髪質はやっぱりステイシーのそれと似ていて、甘い記憶が俺の脳を掠める。
『Give me one last hug.(最後にもう一度だけ私を抱きしめて)』
ステイシーと離れるとき、彼女が必ず言っていた言葉を思い出す。
そのときどき、本当の意味でのラストが永遠に来ないで欲しいことを祈っていた。
俺が手を離したら―――愛しい人はいとも簡単にすり抜けていく。
そう考えて俺は目を開いた。
愛しい?
俺は―――
オータムナルさまが愛おしいと思うのか。
だからこんなにも胸が締め付けられるのか。
―――分からない。
俺が彼のうなじからそっと手を離すと、オータムナルさまも俺の肩から顔を上げ
「私の心配をありがとう。嬉しかった。
それよりもお前の方が顔色悪い気がするが」
指摘されて
「いえ!俺も絶好調です。昨日はちょっと飲み過ぎただけで……」もごもごと口の中で言い訳すると
「そうだったな。昨日はトオルと飲みに行ったのだな」
何故そのことを??
と疑問に思ったが、
「トオルのTwitterにツイートされてたから」
ああ、なるほど。
さっきの愛しさはどこへやら。やっぱり謎だし。
わっかんねーーー!!
P.109
分かりたいと思う反面、分かりたくないと言う気持ちが半分。
オータムナルさまは執務机に向かうと
「今日は地球儀を使わぬのか」と聞いてきた。
「え、ええ。今日は……」
言いかけてコホン、俺はまたも仰々しく咳払いをした。
「今日から――――
少しずつ、俺の話をお聞かせしようかと…」
「紅の?」
「さ、最初に言っておきますけど!!つまらないですからね!
それから聞いてもドン引きしないでくださいよ!!」
しつこいぐらいに前おくと、
「ドンビキなどしぬわ」
とオータムナルさまはちょっと心外そうに眉をしかめる。
「―――しかし、何故話そうと思ったのだ。昨日は頑なに拒んでおったではないか」
「昨日、秋矢さんと飲みに行って―――言われました」
「トオルに?何と?」
「俺は誰に対しても心を開いてないって。自分じゃそんなつもりもないし、そもそも聞かせるほど壮大な歴史を持ってるわけでもないし……
でも秋矢さんに言われて、『そっかー…俺ってそんな風に見られてたんだー』と考え直して、
でも自分のことさらけ出すの得意じゃないし、とりあえずオータムナルさまが知りたいとおっしゃってくれたので、
俺が心を開かない限り、オータムナルさまも開いてくれないんじゃないかってそんな気がして。
何て言ったらいいのか分からないんですけど、俺―――きっと
オータムナルさまとちゃんと向き合いたいんだ」
P.110
「な、長々とすみません。あの…いきなり全部とかは無理ですけど
少しずつ知ってもらいたいな……そしてオータムナルさまのこと少しづつ知れたらなーとか思っちゃったりしまして…」
さっきの勢いはどこへやら、俺の声はどんどん小さくなっていく。
日本語教師としてこの国に派遣されたのに、何一つ教師らしい授業をしていないし。
けれどオータムナルさまは
「少しづつ…か。なるほど、それも良いな。
まるでアラビアンナイトのようじゃないか」
「アラビアンナイト……って、ああ千夜一夜物語」
ポンと手を打つと
「日本では千夜一夜物語と言うのか。響きが美しいな」
美しい…かぁ??
千夜一夜物語って言えば、ある国の王様がお妃さまの不貞を知って殺しちゃうお話だ。その後王様は人を信じられなくなって、嫁いでくるお姫さまたちを次々に殺していく。
そこで側近の娘が妃に名乗り出た。その娘は王様と過ごす夜に楽しい話を聞かせて、続きはまた明日。と言って、続きが気になった王様はその娘を殺さなかった。
娘はその次の夜もその次の夜も楽しい話を聞かせ、千夜を共にしたとき、王様と娘には子供もできていて、その後は幸せに暮らしたと言う話だ。……た気がする。
どっちかって言うと結構残酷なお話だよね。
「夜ではないのが不服だが、まぁよかろう。
一日、また一日過ごすごとにお前のことを知れる。
それはまるでお前の衣服を一枚一枚脱がしていくようで楽しみだ」
オータムナルさまは、サファイヤブルーの目を細め、
その視線だけですべてを絡め取られそうだ。
形の良い唇から赤い舌を少しだけ出し、上唇をゆっくりとなぞる。
その仕草がとても妖艶で、まるで視姦されているようだった。
背中をぞくりと甘い痺れが走り、腰の辺りがぎゅっと疼く。
その妖艶な視線からほんの少し顔を逸らすと、俺は話をはじめた。
P.111
こうして俺とオータムナルさまの千夜一夜物語ははじまった。
「19XX年1月、俺は生まれました。
でも生まれた日にちも、生まれた場所も実は知りません」
「何故だ?お前の両親はお前にそのことを伝えなかったのか?」
オータムナルさまの執務机を挟んで椅子に座っていた俺はちょっと唇を引き結ぶと
「俺は―――両親の顔を知りません。
生まれて間もなく、児童施設の前に捨てられていたようです」
ことさらゆっくり言葉を選んで言った。
「何と………」
オータムナルさまが頬杖をついていた手を解いて目を開いた。
「孤児院って言えばいいんでしょうか。中学にあがるときまで……えっと、俺が12歳までそこで暮らしました。
けれど両親が居ないこと、俺が捨てられたこと―――恨んではいませんでした」
「何故?」
オータムナルさまは先ほどと同じように眉を寄せると切なく瞳を揺らす。
「孤児院には同じ境遇の友達がたくさん居たし、先生も全員やさしかったし、そりゃ悪さをすれば怒られることもあったけれど
あったかいごはんも寝床もあった。
でも小学校に上がると―――周りの友人たちは当然‟家族”があってそれに守られている彼らが―――羨ましい、と
はじめて思いました」
俺が真摯にオータムナルさまに向き合うと、オータムナルさまはそっと手を伸ばしてきて俺の頬を優しく包んだ。
「寂しい―――想いをしてきたのだな。
もっと早くお前と出会えていたのなら、私はお前にそんな想いさせなかったろうに」
P.112
オータムナルさまの言葉と包んでいる手のひらが温かく優しい。
俺も心の底から―――そう思う。
もっと早くオータムナルさまに出会っていたら、俺の人生はもっともっと違ったものだったに違いない。
けれど過去は過去。いつまでも後ろばかり振り返ってはいけないんだ。
俺は包まれた手のひらを包み返した。
「だからオータムナルさまには、カイルさまと仲直りしてほしいんです。
俺には家族が居なかったけれど、オータムナルさまにはマリアさまもカイルさまもどこかで血の繋がった家族が居る。
オータムナルさまやマリアさまには俺の味わった悲しさや寂しさを味あわせたくない。
カイルさまを国外追放にしたら、永遠に会えなくなっちゃんですよ。
それでもいいんですか?
許して―――あげてください。カイルさまを」
P.113
「紅、お前は本当に優しいのだな」
オータムナルさまが俺の頬を撫でながら、優しく優しく目を細める。
「ではカイルさまと……」
「だがそれとこれとは別だ」
オータムナルさまは冷たく言って、それと同時に彼の指先も冷たく冷え切っていくような気がした。
オータムナルさまは俺の手から手を引き抜くと
「紅、お前は何故あのような怖い目に遭っておきながらそんな風に思えるのだ。
私には理解できぬ。
いや、その理解できぬ部分が優しさなのだろうが、だとしたら私は冷たい人間なのだろう」
「そ、そんなことございません!」
慌てて立ち上がると、オータムナルさまはそれを制した。
「お前の気持ちは分かった」
「そ、それじゃ……」
「分かったが、それとこれとは別問題だ。
いくら可愛いお前の頼みでも、それだけは受け入れられん」
そんなー!
「むぅ。約束の時間が迫っている。今日は米国の大統領と食事会合の約束をしているのだ。
お前の話を途中で遮って悪いのだが、今日はここまでだ。すまぬな」
オータムナルさまは一方的に言って、席を立ち上がると
チュ
俺の額にキスをすることだけは忘れずにオータムナルさまは執務室を出て行ってしまった。
P.114<→次へ>
雪に願いを
冬の夜
キミへの気持ちを窓に託しました

たった一言が言えない私は臆病者ですか?
でも今はこれが精一杯
雪に想いを

『次はお天気コーナーです。今日から明日にかけて低気圧が日本の南を発達しながら東北東に進み、明日には日本の東に進む見込みです。
関東甲信地方では今夜から雨が次第に雪に変わり、あす午前中にかけて山沿いを中心に、平野部でも積雪となる所がある見込みです。雪による交通障害、架線や電線、樹木等への着雪、路面の凍結に注意してください』
今朝のワイドショーのお天気キャスターの言葉を思い出したのは、勤めている会社の定時を迎え業務を終えたときだった。
「えー!やだっ!雪降ってるじゃん」と誰からともなく声が挙がり
「ホントだー、私傘持ってきてない」
「どうりで冷えると思った」
と同僚たちが次々と口にする。
またも誰かが「せっかく彼氏に買って貰ったバッグが濡れちゃう」と言い出し、それでもちっとも困った様子ではなく、どこか誇らし気だ。
そしてその周りの女子たちが盛んに羨ましがる。
「いいなー、でもあたし今度のクリスマスにダイヤの指輪ねだっちゃうんだー」と一人の女の子。
「いいなー!」黄色い声に、私は苦笑いを浮かべるしかない。ここでの男の年収と、女の品格は反比例する。いかにいい服を着るか、いかにいいバッグを持つか、いかにいい男を彼氏にするか、年中こんな会話でうんざりする。
かと言って輪に加わらないわけにはいかない。仕事とプライベートの内容こそ比例するのだ。
P.1

「仁科《にしな》さんはいつも素敵な服着てますよね」ふいに一人から話題を振られた。
「えっ、そう?」私は曖昧に笑って言葉を濁した。今日の服装は白いタイトワンピ。腰回りに太いベルトが巻き付いていて、ちょっと豪華に見えるゴールドのバックルがワンポイント。
そして同じくゴールド系のスパンコールが襟元に入ったコートを腕にかけて帰りたいアピール。
シンプルな服装だったけど、流石は目が肥えている女子たち。すぐにそれが高価なものだと見破った。女のチェック程厳しいものはない。私がオシャレをするのは対、男ではなく、彼女たちの為。
「仁科さんてぇ、結婚しないんですかぁ」間延びした話し方が赦されるのはこの年代の特権だ。
「結婚ね……相手がいないから」私は適当にごまかして再び言葉を濁した。
こう言っておけば大抵の女は引き下がる。私が長い間、人付き合いをしてきて、これが最良の方法だと知ったのはつい最近のこと。
私がこの会社に勤めはじめて五年になる。この会社での女性正社員では長いほうだ。後から派遣された若い女の子たちから見れば私なんてお局のようだった。
「そう言えばぁ仁科さん、この前見ちゃったんですぅ」一人の女の子が思わせぶりに口元へ手をやった。
短く切った髪にはパーマがあててあり、傍から見ればマシュマロのように可愛らしい女の子だ。
だが、そんな可愛らしさに惑わされてはいけない。女はいつでも顔の下にしたたかな一面を隠しているのだから。
P.2

「何を?」私は平静を装って取り澄ました。
もしかして“アイツ”と居る所を見られた?と思ってドキリとしたが
「この前の金曜日、青山のイタリアンレストランで、経理の前田さんと一緒にいるところぉ」
ああ、そっちか。とちょっとほっと安堵する。
「ええー!!」周りから黄色い声が飛ぶ。私は思わず頭を押さえたくなった。
そう、確かに経理の前田に誘われて先週の金曜に青山まで行った。
でも食事をしただけで、別に艶かしい関係ではない。だが、ここで重要なのが、経理の前田という男、この会社ではなかなかのハンサムでしかも独身、きさくな性格をしているわりには頼れる上司でもあるのだ。そうゆう男を若い女性社員が放っておくわけがない。
「いいなー、ねえお二人って付き合ってるんですか?」
食事をするイコール男女の関係と、どうして若い子たちはそう短絡的なのだろう。私はこの場から逃げ出したくなった。だけど、この場から立ち去ると認めたことになってしまう。
「別に、ただお食事に誘われただけよ」
「うそー、絶対前田さん仁科さんのこと狙ってるわよぅ。だって、あたしたちがいくら誘っても全然だったのよー。それなのに前田さんは仁科さんのこと」
嫉妬心と羨望の眼差しで見られ、私は思わず後ずさり。
何とか前田との話を切り返し、従業員出入り口から女子の群れに混ざって出てきた所だった。
遠くで派手なエンジン音が聞こえてきて、この狭い路地裏へと近づいてきた。この聞き慣れたエンジン音。私は嫌な予感がして思わず一方通行の標識を見つめた。
「よーう、仁科」黒のポルシェの窓から腕を出し、銜えタバコをしながら九条《くじょう》が手を振っている。
「やっぱり」
私は、今度こそ頭痛をこらえるように頭をしっかりと押さえた。
P.3

「仁科、今終わりか?これから飯でも食わねー?」
この状況を知らずに能天気に笑ってるその整った横っ面に今すぐ張り手を食らわせたい。
「あ、あんたいつ東京に戻ってきたわけ?」私は女の子の群れから一人離れると、九条の車に近づいた。
「あー、悪い。三日ぐらい前かな?この前言ってた日本料理屋行こうぜ」
「あんたっていつも何で急なのよ」
私が声を潜めて九条を睨んでいるときだった。
「えー、仁科さんの彼氏さんですかぁ?かっこいい!」
女の子たちの視線が九条に移った。予想していなかった最悪の事態。
上半身しか見えなかったが、今日の九条は黒いジャケットの中に白いカットソーを着ていて、真冬だって言うのに襟ぐりに濃いサングラスをかけている。いつものように髪をラフにセットしてあって、左耳には輪っかのようなピアスが三つ光っていた。
そう
どこからどーみてもこいつは
ホスト。
P.4

「仁科、今終わりか?これから飯でも食わねー?」
この状況を知らずに能天気に笑ってるその整った横っ面に今すぐ張り手を食らわせたい。
「あ、あんたいつ東京に戻ってきたわけ?」私は女の子の群れから一人離れると、九条の車に近づいた。
「あー、悪い。三日ぐらい前かな?この前言ってた日本料理屋行こうぜ」
「あんたっていつも何で急なのよ」
私が声を潜めて九条を睨んでいるときだった。
「えー、仁科さんの彼氏さんですかぁ?かっこいい!」
女の子たちの視線が九条に移った。予想していなかった最悪の事態。
上半身しか見えなかったが、今日の九条は黒いジャケットの中に白いカットソーを着ていて、真冬だって言うのに襟ぐりに濃いサングラスをかけている。いつものように髪をラフにセットしてあって、左耳には輪っかのようなピアスが三つ光っていた。
そう
どこからどーみてもこいつは
ホスト。
P.4

でも勘違いしてもらっては困る。私はこいつの客じゃない。東京を離れていたのも、大方客の一人と遠征旅行でもしていたのだろう。
「違っ!こいつとは単なる腐れ縁。彼氏とかじゃないから」
と慌てて否定するも秒の単位で噂が回るこの会社で明日の朝には『仁科さんて、ホストに貢いでるらしいよ』とあちこちで言われるに違いない。
くらり、と眩暈が起きた。
腐れ縁、と言うのは間違いない。中学からの同級生だから。
「じゃあ、本命は前田さんですかぁ?」女の子達が興味津々で目を輝かせている。
「前田??ひどいなー、仁科ぁ。俺たち何度もセック……もがっ」
最後の方が言葉にならなかったのは私の手が九条の口を塞いだから。
ふざけんな!何言い出すんだこいつぁ!!
空気読めっつうの!
と言うことを目で訴えると、流石に冗談が過ぎたと思ったのか九条は苦笑い。
「で?行くの?行かないの?」せっかちに聞かれて
「わかったわよ!行くわよ」半ば怒鳴るように九条を睨みつけると、私はそそくさと助手席に回った。
「それじゃ、私はこれで。お先に」女の子たちにはなるべく平静を装って、にこやかに手を振る。
ため息をついて車の助手席を開けると、運転席から九条が笑顔で手を差し伸べてきた。
「ただいま、仁科」
昔とちっとも変わらない笑顔。眉が下がり、目を細める、優しい笑顔。そして時々その低い声で呼ばれる、自分の名前。何だかくすぐったいが、この笑顔を向けられたら、たとえ九条の勝手に振り回されても、赦せてしまう。
「……おかえりなさい」私は俯くと、小さく返事を返した。
P.5

前述した通り私と九条とは中学からの付き合いだ。かれこれ十年以上の付き合いになる。十年、と言う歳月は長く感じられるけれど、その間に音信不通になったり、そしてどこからか連絡先を入手して電話を寄越して来たり、をだらだらと繰り返している。
でも、私たちははっきりと『付き合って』はいない。もちろん九条のブラックジョークの『体の関係』もない。
あるのは中学生から変わらないノリと
私が九条のこと「好き」
と言うことだけ。歳を重ねて、九条がホストになって……あ、今はホストじゃなくホスト店を経営してるオーナー様でもあったかしら。とにかく環境は変わったものの、不変的な何かは確実に存在している。
パワーウィンドウの外をちらほらと雪が降っていた。
「北海道行ってきたんだ~土産に蟹買ってきてやったぞ」と九条は運転しながらどこか楽しそう。
「北海道……ここより雪が多そうね」ぼんやりと呟きながら、九条に気づかれない程度にこっそりと、外気との差で曇った窓ガラスに、人差し指で
『好き』
と書く。
私の書いた文字は私の体で隠れて九条からは見えない。
「蟹すきしようぜ~、お前んちで」
「何であんたを一々上げないといけない?」
言い合いをしながら、やがて私のマンションに着く頃にはみぞれになった大粒の白いものが私の『好き』をかき消す。
「だってお前んち床暖あるじゃん?」
「そんな理由かよ」
中学生から変わってないこの関係とノリ。
今はまだ―――
この関係でいいや。
~FIN~
P.6

