七回目の満席
『空席のアリーナ席』
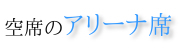

毎年、秋のはじめ…まだ夏の名残を残したこの微妙な季節に、それは届く。
白い封筒に入った、日本でもトップレベルの人気を誇る某アイドルのライブチケット。
アリーナ席の最前列。
そしてホテルの名前とナンバーが書かれたメモ。
それはもう七通目になります。
P.1

10cmヒールを鳴らし、毎日一房のほつれもなく髪をまとめあげ、窮屈な細身のスーツに身を包みながらも
私の仕事は、某主婦向けの雑誌の「今日の一番」と言う街の風景を載せたたった半ページにも満たない雑誌のコーナーを飾ると言うもの。
二十代前半はそれなりにバリバリ働いていたつもり。
人気のファッションコーナーから、芸能コーナー、いっときはやりがいのある社会記事を扱ってもいた。
けれど私の築き上げてきたキャリアなんてクソみたいなものだ。
と思い知らされた。
三十歳を目前に飛ばされたのが今の部署。
誰も目に留めるようなことが無いような小さなコーナーを受け持って一年。
前は大手出版社の名前が入った名刺を出すのが誇りでもあったし、その名前には威力があり、自信もあった。
でも今は―――
かつて抱いていたあの感情はどこにもない。
P.2

会社が「自主退職」を促しているのは分かりきっていた。
それでも、いくら部署を変え異動させられようと降格扱いされようと、その度に「なにくそ」としがみついていたのは私の意地。
この九年彼氏なし。
毎年会社の「社内イチ冷たい女」または「結婚したくない女」ナンバー1を目下更新中のこの私。
あとに残るのは仕事だけでしょう?
なんてかっこつけて言うけど、そんないいものじゃない。
てかこの歳で転職とかできるほど世間は甘くない。
大手出版社の経歴を見れば、経験優遇されるどころか「何故退職したのか」と言う理由を問われるに違いない。
用はこの会社で、まるで隠されるようにひっそりと奥まった狭い部屋の、これまた小さなデスクが私の居場所―――
その席を必死で守ろうとしている私は、もっとアホ。
いえ…
本当は期待していた。
このままがんばればまた「彼」に会えると、どこかで期待していた。
転職もできないような女が見る夢は
もっと馬鹿げている。
大好きな人のお嫁さん。
P.3

「会えるかも」なんて思い上がりで、また「彼」と一緒に仕事をしたい、まだ彼の好きだったバリバリ働く女でありたい―――
プライドが邪魔して、変な夢見て
でもそれは思い上がりでしかない。
実際はひと月に何千と投稿のある写真から「これ」と言う一枚を選別して、もっともらしい原稿を書き、読まれもしないコーナーに記事を載せる。
それを全部一人でこなさなければならない。
プライドと引き換えに私は自分の時間と生活を犠牲にして、疲れ果てていた。
どうせがんばったって読まれなもしない一ページなのに。
##FC.#999999##逃げ出したい。##FE##
はじめて「あの時」の「彼」の言葉の意味が分かった。
逃げ出して、結婚相談所で紹介された自分に見合う無難な人と出会い、結婚する。
それもいいかも…婚活しよっかなぁ
…半ば諦めかけていたとき。
一人のマンション…誰も居ない暗いマンション、
「おかえり」と出迎えてくれる人のいない寂しい玄関先でヒールの靴を投げ出し、
ポストに投函されていたダイレクトメールの山をダイニングテーブルに投げ出し、
もうどうでもいいや、って気分になってるとき。
それを見つけるまでは。
白い封筒。
一年に一度だけ送られてくるそれ。
私はその封筒の端を目に入れダイレクトメールの山を掻き分け、その手紙を手にとった。
住所はこのマンションが記されていて、
“安藤 環 様”
と「彼」直筆の文字を目に入れたとき、何かがこときれた。
私は封筒の封を切り、中身を取り出すとやはり毎年送られてくるライブチケットとメモが一枚。
“いつもの部屋にチェックインして”
と書かれていて、
「いつも…って一度も私たちあの部屋で会ったことないじゃない…」
思わず独り言を漏らした。
でも『いつも』で通じるのは、指定されるホテルと部屋番号がいつも一緒だからだ。
チケットの日付は
―――9月18日。
私は目を細めてカレンダーを目配せ。
「彼」に会うのは
実に簡単なことだったのだ。
必要なのは一歩だった。
P.4

アリーナ席の最前列。
一つだけ空いた席が指定席のようにぽっかりと開いていて、私は何度もチケットの席ナンバーを確認した。
「やっぱりここ…」
目の前には本当にすぐステージ。
立派な装飾が施されたステージを見上げ、そして辺りを見渡すと六階まで吹き抜けの大きなホールに席が続いている。
収容客数は45,000人の大きなホール。
この付近では一番の広さを誇るホールだ。その席はほとんど余すことなく若い女の子たちで埋まっていた。
以前仕事の取材でこのホールを訪れたときは何とも思わなかったのに、
今はこの大きなホールに私の方がドキドキ…緊張してきた。
コンサートが始まるのを今か今かと目を輝かせ「彼ら」の登場を待ち望んでいるファンの子たち。
彼女たちの若い輝きの中、私は「彼」の目に留まることができるのだろうか。
会社帰りのスーツの上に、目印で彼がくれたストールを掛けてきたけど。
こんな暗い中それを見分けられるのかどうかも不安だ。
大体どのコンサートでもステージは光の波でほとんど席が見えないって…常識だ。
それでも…たとえ彼が私を見つけてくれても、周りの輝きの中、私は彼の目にどう映るだろう。
望めばダイヤモンドみたいな女の子を手に入れることができるだろう彼にとって、私は今や道端に転がった石ころのように存在価値のない女だ。
だって彼は言ってくれた。
『がんばってるあんたが好き。
がむしゃらで向こう見ずで、プロ意識が強くて―――
俺にはない強さを持ってる環が』
私は今、彼が好きだと言ってくれたものを何も持っていない。
ただプライドに縋り付くだけの惨めな女だ。
『俺の夢はね~
こんな小さなホールじゃなくて、でっかい都市ツアーで思い切り歌うの。
テレビ局の歌番組のときみたに口パクじゃなくて、全部リアルな俺の声で
何千万と居るファンを魅了できたらいいな』
まるで少年のように、無邪気に顔を輝かせて笑った彼。
君の夢……
叶ったね。
君の活躍は雑誌やテレビで見てたから全部知ってる。
でも
ねぇ
あなたは私の“夢”を覚えている?
P.5

大きな爆発音とも呼べる音で会場が暗くなり、場内が一気に色めきたった。方々で悲鳴のような歓声が聞こえる。
ホールの中が暗くなり、ファンの子たちが振るペンライトの明かりだけがまるでホタルの光のように美しく左右している。
再び爆音。
一曲目のイントロがはじまり、ステージのあちこちで炎の柱があがった。
びっくりして目をまばたいていると、それはどうやら演出だったらしく派手な演出と共に
「彼ら」が跳び上がるように姿を現した。
「「「「「キャーッ!!!!」」」」」
まるでホールを揺るがすような女の子たちの悲鳴に似た歓声の中、堂々と登場したのは今も輝く日本のトップアイドル。
彼らの活躍をテレビや雑誌で見ない日がないほど、今や売れっ子となった男性五人組の
「Place」の姿だった。
その瞬間―――
ああ、彼らの輝きは七年前のそれよりも増し、若い彼女たちよりも彼女たちが振るペンライトの光よりも
眩しい。
P.6

センターの右隣に位置する「彼」……
リードボーカルの一人でもある彼。
ゼン
ううん…禅夜(Zenya)
「キャーッ!!ゼンッ!ゼンーーー!!」
狂ったように彼の名前を呼び続けるファンの歓声にもろともせず、彼はしなやかで…一方まるで一寸の乱れもない機械的なリズムと動きでステージを舞い
魅了する。
前はその名前すら知らない子がほとんどだったって言うのに、いつの間にか若いファンの子たちに当たり前のように名前を呼ばれるようになっている。
禅夜―――
今、この瞬間…はあなたにこんなに近いのに―――
世界一遠い。
P.7

耳に心地よいテノールのレジスターは、七年前より音域を広げ、さらに歌唱力の成長を感じた。
元々歌は上手かったのだ。
一曲目も中ほどまでいくと、メンバーは洗練された歌と五人揃っての乱れのないダンスでファンたちを魅了し前に進み出る。
女の子たちの悲鳴が一段と大きくなっていき、
ステージの端まで来た禅夜はファンサービスの為か、席を一望。
眺める視線が私のところで一瞬ぴくりと止まり、
大きな目をさらに広げてまばたきも忘れたかのようにただじっと一点を見つめる。
それは予想もしなかったことに驚いたときの彼の癖だ。
次の瞬間は片目だけを僅かに細め、キリリとした眉の端がぴくりと小さく動く。
それも変わっていない。
思いきり目があったのに、禅夜は私から視線を逸らして歌とダンスに集中する。
七年前は―――
こんな大きな都市の大きなホールでライブツアーをするようなグループではなかった。
私が彼ら…『Plase』にはじめて会ったのは、彼らがまだ駆け出しのとき。
私は当時、女性雑誌の部署で芸能コーナーを受け持っていた。
有名女性ファッション雑誌の2Pを飾るコーナーで、新人アイドルやモデル、俳優などを紹介するコーナーは割と読者年齢が若い女の子たちにウケが良かった。
その時の取材で会ったのだ。
P.8<→次へ>

雪に願いを
冬の夜
キミへの気持ちを窓に託しました

たった一言が言えない私は臆病者ですか?
でも今はこれが精一杯
雪に想いを

『次はお天気コーナーです。今日から明日にかけて低気圧が日本の南を発達しながら東北東に進み、明日には日本の東に進む見込みです。
関東甲信地方では今夜から雨が次第に雪に変わり、あす午前中にかけて山沿いを中心に、平野部でも積雪となる所がある見込みです。雪による交通障害、架線や電線、樹木等への着雪、路面の凍結に注意してください』
今朝のワイドショーのお天気キャスターの言葉を思い出したのは、勤めている会社の定時を迎え業務を終えたときだった。
「えー!やだっ!雪降ってるじゃん」と誰からともなく声が挙がり
「ホントだー、私傘持ってきてない」
「どうりで冷えると思った」
と同僚たちが次々と口にする。
またも誰かが「せっかく彼氏に買って貰ったバッグが濡れちゃう」と言い出し、それでもちっとも困った様子ではなく、どこか誇らし気だ。
そしてその周りの女子たちが盛んに羨ましがる。
「いいなー、でもあたし今度のクリスマスにダイヤの指輪ねだっちゃうんだー」と一人の女の子。
「いいなー!」黄色い声に、私は苦笑いを浮かべるしかない。ここでの男の年収と、女の品格は反比例する。いかにいい服を着るか、いかにいいバッグを持つか、いかにいい男を彼氏にするか、年中こんな会話でうんざりする。
かと言って輪に加わらないわけにはいかない。仕事とプライベートの内容こそ比例するのだ。
P.1

「仁科《にしな》さんはいつも素敵な服着てますよね」ふいに一人から話題を振られた。
「えっ、そう?」私は曖昧に笑って言葉を濁した。今日の服装は白いタイトワンピ。腰回りに太いベルトが巻き付いていて、ちょっと豪華に見えるゴールドのバックルがワンポイント。
そして同じくゴールド系のスパンコールが襟元に入ったコートを腕にかけて帰りたいアピール。
シンプルな服装だったけど、流石は目が肥えている女子たち。すぐにそれが高価なものだと見破った。女のチェック程厳しいものはない。私がオシャレをするのは対、男ではなく、彼女たちの為。
「仁科さんてぇ、結婚しないんですかぁ」間延びした話し方が赦されるのはこの年代の特権だ。
「結婚ね……相手がいないから」私は適当にごまかして再び言葉を濁した。
こう言っておけば大抵の女は引き下がる。私が長い間、人付き合いをしてきて、これが最良の方法だと知ったのはつい最近のこと。
私がこの会社に勤めはじめて五年になる。この会社での女性正社員では長いほうだ。後から派遣された若い女の子たちから見れば私なんてお局のようだった。
「そう言えばぁ仁科さん、この前見ちゃったんですぅ」一人の女の子が思わせぶりに口元へ手をやった。
短く切った髪にはパーマがあててあり、傍から見ればマシュマロのように可愛らしい女の子だ。
だが、そんな可愛らしさに惑わされてはいけない。女はいつでも顔の下にしたたかな一面を隠しているのだから。
P.2

「何を?」私は平静を装って取り澄ました。
もしかして“アイツ”と居る所を見られた?と思ってドキリとしたが
「この前の金曜日、青山のイタリアンレストランで、経理の前田さんと一緒にいるところぉ」
ああ、そっちか。とちょっとほっと安堵する。
「ええー!!」周りから黄色い声が飛ぶ。私は思わず頭を押さえたくなった。
そう、確かに経理の前田に誘われて先週の金曜に青山まで行った。
でも食事をしただけで、別に艶かしい関係ではない。だが、ここで重要なのが、経理の前田という男、この会社ではなかなかのハンサムでしかも独身、きさくな性格をしているわりには頼れる上司でもあるのだ。そうゆう男を若い女性社員が放っておくわけがない。
「いいなー、ねえお二人って付き合ってるんですか?」
食事をするイコール男女の関係と、どうして若い子たちはそう短絡的なのだろう。私はこの場から逃げ出したくなった。だけど、この場から立ち去ると認めたことになってしまう。
「別に、ただお食事に誘われただけよ」
「うそー、絶対前田さん仁科さんのこと狙ってるわよぅ。だって、あたしたちがいくら誘っても全然だったのよー。それなのに前田さんは仁科さんのこと」
嫉妬心と羨望の眼差しで見られ、私は思わず後ずさり。
何とか前田との話を切り返し、従業員出入り口から女子の群れに混ざって出てきた所だった。
遠くで派手なエンジン音が聞こえてきて、この狭い路地裏へと近づいてきた。この聞き慣れたエンジン音。私は嫌な予感がして思わず一方通行の標識を見つめた。
「よーう、仁科」黒のポルシェの窓から腕を出し、銜えタバコをしながら九条《くじょう》が手を振っている。
「やっぱり」
私は、今度こそ頭痛をこらえるように頭をしっかりと押さえた。
P.3

「仁科、今終わりか?これから飯でも食わねー?」
この状況を知らずに能天気に笑ってるその整った横っ面に今すぐ張り手を食らわせたい。
「あ、あんたいつ東京に戻ってきたわけ?」私は女の子の群れから一人離れると、九条の車に近づいた。
「あー、悪い。三日ぐらい前かな?この前言ってた日本料理屋行こうぜ」
「あんたっていつも何で急なのよ」
私が声を潜めて九条を睨んでいるときだった。
「えー、仁科さんの彼氏さんですかぁ?かっこいい!」
女の子たちの視線が九条に移った。予想していなかった最悪の事態。
上半身しか見えなかったが、今日の九条は黒いジャケットの中に白いカットソーを着ていて、真冬だって言うのに襟ぐりに濃いサングラスをかけている。いつものように髪をラフにセットしてあって、左耳には輪っかのようなピアスが三つ光っていた。
そう
どこからどーみてもこいつは
ホスト。
P.4

「仁科、今終わりか?これから飯でも食わねー?」
この状況を知らずに能天気に笑ってるその整った横っ面に今すぐ張り手を食らわせたい。
「あ、あんたいつ東京に戻ってきたわけ?」私は女の子の群れから一人離れると、九条の車に近づいた。
「あー、悪い。三日ぐらい前かな?この前言ってた日本料理屋行こうぜ」
「あんたっていつも何で急なのよ」
私が声を潜めて九条を睨んでいるときだった。
「えー、仁科さんの彼氏さんですかぁ?かっこいい!」
女の子たちの視線が九条に移った。予想していなかった最悪の事態。
上半身しか見えなかったが、今日の九条は黒いジャケットの中に白いカットソーを着ていて、真冬だって言うのに襟ぐりに濃いサングラスをかけている。いつものように髪をラフにセットしてあって、左耳には輪っかのようなピアスが三つ光っていた。
そう
どこからどーみてもこいつは
ホスト。
P.4

でも勘違いしてもらっては困る。私はこいつの客じゃない。東京を離れていたのも、大方客の一人と遠征旅行でもしていたのだろう。
「違っ!こいつとは単なる腐れ縁。彼氏とかじゃないから」
と慌てて否定するも秒の単位で噂が回るこの会社で明日の朝には『仁科さんて、ホストに貢いでるらしいよ』とあちこちで言われるに違いない。
くらり、と眩暈が起きた。
腐れ縁、と言うのは間違いない。中学からの同級生だから。
「じゃあ、本命は前田さんですかぁ?」女の子達が興味津々で目を輝かせている。
「前田??ひどいなー、仁科ぁ。俺たち何度もセック……もがっ」
最後の方が言葉にならなかったのは私の手が九条の口を塞いだから。
ふざけんな!何言い出すんだこいつぁ!!
空気読めっつうの!
と言うことを目で訴えると、流石に冗談が過ぎたと思ったのか九条は苦笑い。
「で?行くの?行かないの?」せっかちに聞かれて
「わかったわよ!行くわよ」半ば怒鳴るように九条を睨みつけると、私はそそくさと助手席に回った。
「それじゃ、私はこれで。お先に」女の子たちにはなるべく平静を装って、にこやかに手を振る。
ため息をついて車の助手席を開けると、運転席から九条が笑顔で手を差し伸べてきた。
「ただいま、仁科」
昔とちっとも変わらない笑顔。眉が下がり、目を細める、優しい笑顔。そして時々その低い声で呼ばれる、自分の名前。何だかくすぐったいが、この笑顔を向けられたら、たとえ九条の勝手に振り回されても、赦せてしまう。
「……おかえりなさい」私は俯くと、小さく返事を返した。
P.5

前述した通り私と九条とは中学からの付き合いだ。かれこれ十年以上の付き合いになる。十年、と言う歳月は長く感じられるけれど、その間に音信不通になったり、そしてどこからか連絡先を入手して電話を寄越して来たり、をだらだらと繰り返している。
でも、私たちははっきりと『付き合って』はいない。もちろん九条のブラックジョークの『体の関係』もない。
あるのは中学生から変わらないノリと
私が九条のこと「好き」
と言うことだけ。歳を重ねて、九条がホストになって……あ、今はホストじゃなくホスト店を経営してるオーナー様でもあったかしら。とにかく環境は変わったものの、不変的な何かは確実に存在している。
パワーウィンドウの外をちらほらと雪が降っていた。
「北海道行ってきたんだ~土産に蟹買ってきてやったぞ」と九条は運転しながらどこか楽しそう。
「北海道……ここより雪が多そうね」ぼんやりと呟きながら、九条に気づかれない程度にこっそりと、外気との差で曇った窓ガラスに、人差し指で
『好き』
と書く。
私の書いた文字は私の体で隠れて九条からは見えない。
「蟹すきしようぜ~、お前んちで」
「何であんたを一々上げないといけない?」
言い合いをしながら、やがて私のマンションに着く頃にはみぞれになった大粒の白いものが私の『好き』をかき消す。
「だってお前んち床暖あるじゃん?」
「そんな理由かよ」
中学生から変わってないこの関係とノリ。
今はまだ―――
この関係でいいや。
~FIN~
P.6

